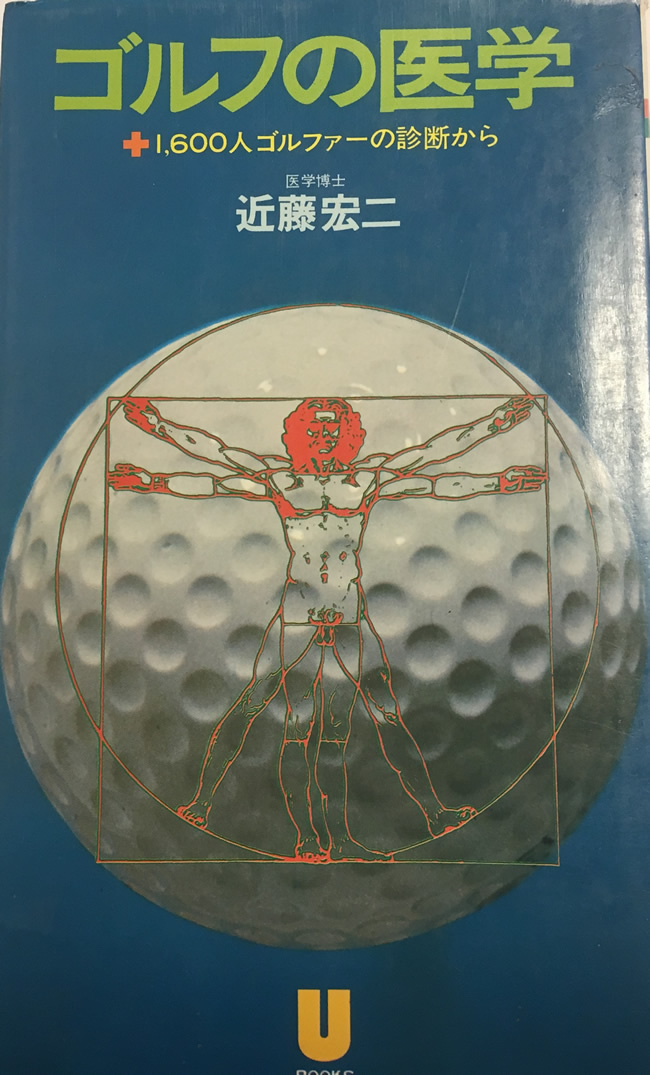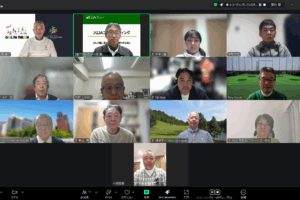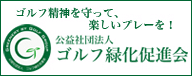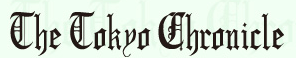※本稿は月刊ゴルフ用品界2016年11月号「北 徹朗の産学協同奮戦日記」への掲載原稿を再編集したものです。
書評:『ゴルフの医学-1600人のゴルファー診断から-』(近藤宏二著/株式会社住宅新報社/1977年)
近年、大学はユニバーサル・アクセスの段階(誰もがいつでも自らの選択により学ぶことが可能)を迎えた。これは1970年代に米国の社会学者マーチン・トロウが提唱したモデルによるものだが、日本の現状(定員割れ大学が私大全体の44.5%)はそれを遥かに超えてしまっているかもしれない。ゴルフも同様に、かつては一部の高貴な人のたしなみだったが、今や大衆化し、筆者が従事する大学業界と同様に供給過剰と言わざるを得ない状況だろう。
今から40年前(1977年)に住宅新報社から面白い書籍(絶版)が発行されている。本書が発行された当時、ゴルフ場数は1322箇所(NGK資料より)だが、まだまだ特別なイメージの強いスポーツであった頃ではないか。
80年代後半から90年代前半頃、ゴルフ場における突然死の問題がクローズアップされるようになったが、本書にはそのかなり前の段階からの事故事例が詳細に紹介され、それへの対処や提言も具体的に書かれている。
近年、ハーフで昼を挟むプレースタイルに拘らない多様なパッケージが提供されているが、本書では「昼食後に2時間余り4キロ程度の歩きとクラブを振る適度な運動によって、食後の血糖の上昇が抑えられるゴルフは糖尿病に効く」とし、近藤氏が主催した「ゴルフ人間ドッグ」に参加した糖尿病患者や予備軍の長期観察症例研究も多数紹介されている。
ゴルフの大衆化、コア・ゴルファーが高齢化した今日、『昼食を伴うゴルフこそ健康的なスポーツ』というのは古くて新しい発想になり得るのかもしれない。