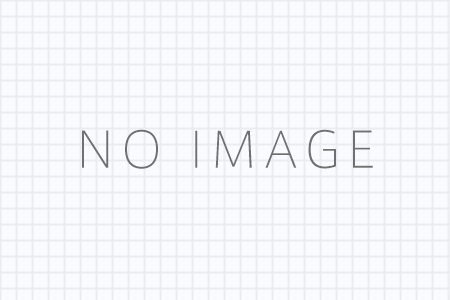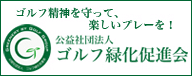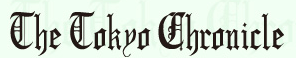今年の夏、暑い盛りに行った滋賀県のあるゴルフ場で、車から降りジャケットを抱えて入ろうとすると「上着を着てお入りください」と入り口にいた係員に注意された。ドアを一歩はいれば直ぐに脱ぐのだから、別に着なくてもいいではないかと思いながら、指示に従って暑いのを我慢しフロントに向かった。古いゴルフ場には厳しいしきたりが残っているんだなと感じたものだった。
秋口の男子トーナメント会場を訪れた時の事である。クラブハウスの食堂の中央に陣取った若手の人気プロが、帽子をかぶったままファンらしき人たちに囲まれて飲み物を飲んでいた。その内だれかが注意するか、本人が気付くだろうと見ていたが、食堂のスタッフも大会関係者も見て見ぬふり。何か割り切れない気分だった。
プロゴルファーがゴルフ場に所属していた時代は、先輩のプロやコースのメンバーに 礼儀、作法 を教え込まれた。今はたとえエチケットに反する事をしても、注意する人はいなくなってしまったのだろうか。
その帽子だがテレビのインタビューを受ける際、また表彰式で帽子を脱がないプロが多くなってきたように感じる。かつて青木功プロや樋口久子プロ(現・日本女子プロゴルフ協会会長)は、必ずキャップやバイザーを取って受け答えしていたが、それを当たり前のように受け止めていた。先頃のダンロップフェニックスに初出場し初優勝したD・デュバルが、愛用のサングラスと帽子を脱いでインタビューに応じていたのについ好感を持って見てしまった。
帽子を付けたまま表彰を受けるのはトーナメントの主催者に対して失礼ではないのだろうかと思い、あるプロが所属するゴルフ用品メーカーに帽子の件を聞いてみた。ところが、意外な答えが返ってきたのには驚かされた。「出来る限りテレビカメラを向けられた時は、帽子をかぶって写ってほしいと言ってあります」いわば、PRに協力するのも契約のうちと言うのである。ゴルフクラブやボールの秒単位のコマーシャルに何千万円も払っているメーカーにとって、契約プロが自社のロゴを露出するのは宣伝効果の一つと見ている。プロがかぶる帽子には正面や側面によく目立つようにマークが入っている。表彰式でも堂々とかぶたままトロフィーを受けるのはPRのためだったとは、こちらが認識不足だったのだろうか。
日本オープンに初めて優勝した手嶋多一プロが、ラウンド中はかぶっていなかった帽子をプレー終了後、バイザーをつけ表彰式に臨んだことにもこれで納得がいく。契約社に対して最後に義理を果たしたかったのだろう。かつて杉原輝雄プロが『君ら若いプロは早く皆さんに顔を覚えてもらわなあかん。帽子をかぶらんとプレーせえ』帽子をしていたのでは顔が見えにくい、だからたとえ夏の暑い日でも無帽でプレーをと言ったのは過去の話になってしまった。
トッププロの顔ぶれ、トーナメントの様式は時代とともに大きく様変わりしてきたがエチケット、マナーはゴルフの根本理念として忘れないでほしい。
文屋源也(ぶんやもとや)
1934年生まれ。関西大学卒業後、日刊スポーツ新聞社(大阪本社)入社。オリンピックを中心としたアマスポーツを担当。60年からはゴルフ担当となる。89年同社退社後、米ロサンゼルスでの執筆活動、(社)日本ゴルフトーナメント協会勤務を経て、現在は大阪新聞、月刊ゴルフメイトなどで執筆中。