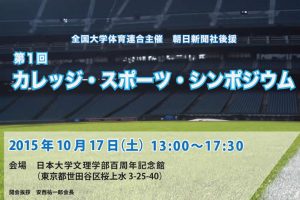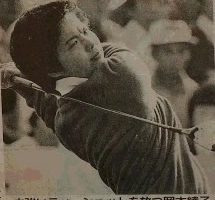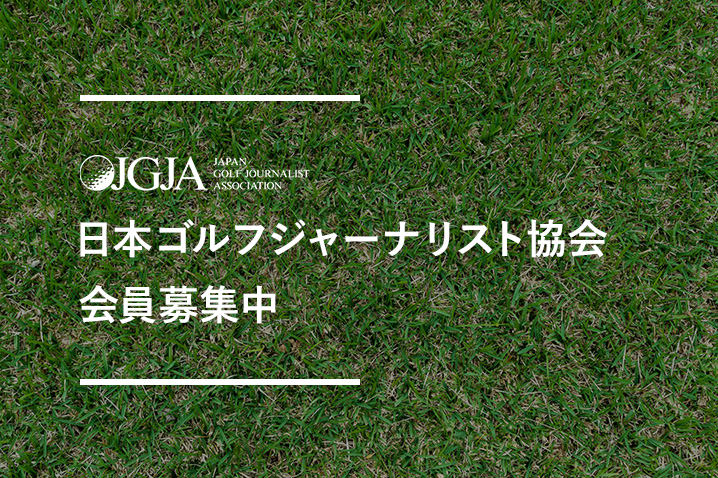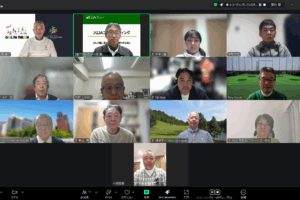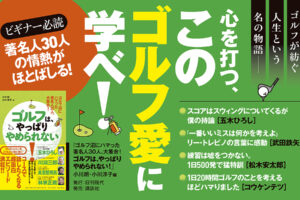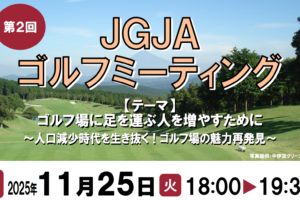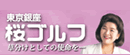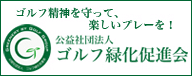日経電子版2016年11月10日配信
国内男子ゴルフツアーも大詰めを迎えた10月、米国のPGA(米プロゴルフ協会)ツアーからビッグニュースが連続して飛び込んできた。
まずは18日に、米国内で展開しているチャンピオンズ・ツアー(シニアツアー)の新設大会「JAL選手権」を2017年9月に日本で開催すると発表。賞金総額250万ドル(約2億6000万円)と日本では破格の規模で、68人の出場者のうち日本からは8人だけが招待出場となる。
さらに26日には米ツアーのアジア地区の拠点となる「東京支社」の開設も発表した。
30日には中国・上海からもっと大きな衝撃が伝わってくる。米ツアーの「HSBCチャンピオンズ」で松山英樹が2位に7打の大差をつけて圧勝。日本ではカウントされないが、たった1試合で、この時点での国内獲得賞金レース1位に相当する162万ドル(約1億7000万円)の優勝賞金を獲得した。
■米ツアー、海外に市場求める
米ツアーがらみのこれらの出来事を、「やった、やった」と大喜びするのは短絡的すぎる。ひょっとしたら、これらは、日本のプロゴルフ界にとって、明治維新につながったペリー来航にも似た一大事になるかもしれないからだ。
この米ツアーの海外戦略に対処するため、今度こそ本気で国内プロゴルフ界の統一を実行すべきだろう。
米ツアーの海外での試合開催は近年、従来のカナダに加え、メキシコ、バハマ、マレーシア、中国などと急増している。理由の一つは、米国内でのスポンサー獲得が目いっぱいの状態になり、市場を海外に求めざるを得なくなったことがある。
「では日本では?」とも考えられるが、例えば松山が勝ったHSBCチャンピオンズの賞金総額は950万ドル(約10億円)で、開催費用などを加えると最低でも20億円になる。今の日本の経済状況の中で手を挙げるスポンサーを見つけるのは難しい。
そんなレギュラーツアーに比べて費用が3分の1から4分の1で開催できるシニアツアーは、頃合いの日本開催で、支社開設とともに、絶好の「橋頭保(きょうとうほ)」を築いたといえる。
■次はレギュラーツアーの日本開催か
来年のシニア大会が成功したら、次に米ツアーが考えてくるのは、レギュラーツアーの日本開催だろう。松山や石川遼らの米ツアーでの活躍次第では、ビッグスポンサーが名乗りを上げないとも限らない。実現したら、もろに影響を受けるのは、スポンサー探しで苦労している国内ツアーである。
そうなる前に、日本プロゴルフ協会(日本プロ協会)と日本ゴルフツアー機構(日本ツアー)の2本立てになっている今の状況を一日でも早く解消すべきだ。
国内ツアーは、もとは日本プロ協会が管理・運営していたが、1999年にツアー部門が「けんか別れ」のような形で独立して現在に至っている。
その後、再統一が何回か話題になったが、いまだに実現していない。現在の日本プロ協会の会長は、かつて日本ツアーの会長を務めていた倉本昌弘で、一方の日本ツアーの会長にはプロゴルファーの象徴のような青木功が就いている。
「腸ねん転」か「たすき掛け」のようで、これも一時的なもので、統一の足掛かりかと思われたが、一向に動きがない。
この話になると、関係者から必ず「米国も2つになっている」という声が上がる。しかし、スケールがまるで違う。
米PGAの会員は約2万8000人。クラブプロやレッスンプロ、ゴルフ関連業界のスペシャリスト養成など、事業が完全に軌道に乗っている。片や日本プロ協会は、トーナメントプロを入れても会員は5000人強でしかない。
■みんなで知恵出し合って立て直して
ツアーの差はさらに大きい。今年の総賞金額は、日本ツアーの約35億円に対して、米ツアーは10倍の約350億円。かつては太平洋を挟んで「二大ツアー」といわれたが、いまや足元にも及ばない。
カリフォルニア州より面積が小さい日本で、プロ協会だ、ツアー機構だなどと言い張っているほうがおかしい。一緒になり、みんなで知恵を出し合って、すべての面でプロゴルフ界を立て直してほしい。
松山の米メジャー大会優勝の実現に期待がかかり、人気に片寄りがあるとはいえ、男子プロゴルフが再び注目され始めた今を逃すと、「元のさや」に収まるチャンスはなくなる。