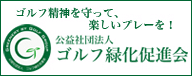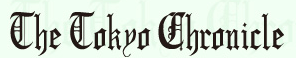77歳まで土井さんは「トーナメントのプレスルームの主」のような存在だった。試合会場に行けばだいたいいつでも会うことが出来た。ところが昨年9月ごろから体調がよくないと言い、10月、日本オープンの会場(日光CC)にはついに姿を見せなかった。
入院先の大船の病院に見舞うと「左の腎臓がちょっと・・・」ということだった。だけどもベッドに起き上がって、1時間近くたっても話をやめようとしない。「これならたいしたことはなさそうだ」と思いながらも、「土井さん、疲れるから」と言って帰ってきた。 年が明けて間もなくもう一度見舞いに行ったときも「暖かくなったら理事会にも行くよ」と言っていた。その後も電話をすると「そのうち必ず出て行くから」と言うので、まさかこんなこになるとは思ってもいなかった。 1988年、日本ゴルフジャーナリスト協会発足と同時に会長をお願いし、今年で17年目になる。日刊スポーツ新聞では定年までゴルフを担当、フリーになってからも最後の最後まで現役を貫かれ、全米や全英オープンの取材も続けてこられた。日本のゴルフジャーナリストの草分けであると同時に、ゴルフの生き字引のような存在でもあった。
ワープロもPCもついに使わなかった人で、プレスルームではただ一人最後まで「手書き」を貫いた人でもある。それがまたボールペンで、達筆で、まるで清書でもしたかのような、まったく直しを入れた形跡のない綺麗な原稿だった。背筋をしゃんと伸ばし、すらすらとペンを走らせていた土井さんの姿が目の前にある。
見上げるような長身で学生時代はスキーの選手だったので、強い足腰でゴルフもうまく(オフィシャルハンディ4までいった)、なおかつよく飛んだ。ビッグスギといわれた杉本英世でさえ、当りがあまりよくないと置いていかれることがあった。四冠王の村上隆よりは間違いなく飛んだ。
東京オリンピックの昭和39年、土井さんの勤める日刊スポーツ新聞社の子会社(日刊スポーツ出版社)で私はゴルフの編集者としてスタートした。新聞記者といえば無愛想でとっつきが悪いという印象が私にはあった。だけども土井さんはまったく違っていた。大学を出たばかりの駆け出しの記者にも噛んで含めるようにゴルフを一から教えてくれるのだった。
「ゴルフをやっているか」と土井さんに聞かれ、「忙しくて・・・」というと、次のように言われたのを今でも忘れることができない。「銀行勤めの人が忙しいからゴルフが出来ないというのなら分かるけど、ゴルフ雑誌を作っているものが忙しいからゴルフが出来ないというのはどういうことだ」
私が一生懸命ゴルフをやるようになったのはそれからである。有難うございました。安らかにお休みください。