日本ゴルフジャーナリスト協会(JGJA)では、2025年度からの新たな試み「JGJAゴルフミーティング」を企画しました。その第1回が9月9日(火)に開催され、JGJA会員10名、ゲスト1名の計11名が参加しました。
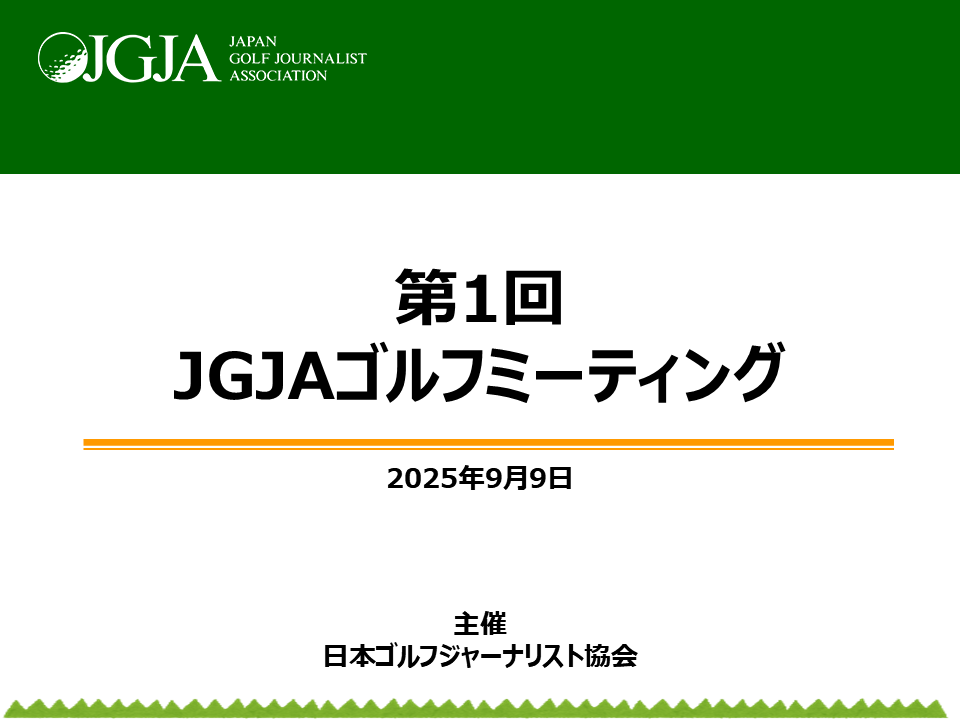
JGJAゴルフミーティングは、会員相互のコミュニティ形成や会員活動を支援することを目的に、主にオンラインで情報交換の場を設けるものです。このことを通じてゴルフ業界の活性化を図ります。
第1回のテーマは、「日本のゴルフ場を魅力あるものにするために」です。
(一社)ゴルフトライアスロン協会の代表、松尾俊介氏(JGJA会員)に約50分ご講演いただき、後半の約30分、意見交換会を行いました。進行役は筆者(小森)が務めました。
当初、松尾氏の講演が30分、後半の意見交換会が60分の予定でしたが、松尾氏の講演内容がとても濃かったため時間配分を変更。講演を40~50分とし、その分意見交換会の時間を短くしました。そして第2回の同ミーティング(11月25日開催予定)を同じテーマの続編とし、ここで意見交換会の時間を多く設けて議論を深掘りすることにしました。
■「第1回JGJAゴルフミーティング」の詳細は ▷こちら
ゴルフ関係者は改革のための議論を
松尾氏の講演は、ソフトな語り口調で淡々と話しながらも、日本のゴルフ業界に警笛を鳴らす熱のこもったものでした。
講演は、日本のゴルフ界が抱える「5つの問題」からはじまり、「ゴルフ産業はゴルフ場が核となっている。ゴルフ場が減少すればゴルフ産業も衰退する」と訴えました。
つまり、直接ゴルフ場を営んでいるわけではない事業者、例えば練習場、ゴルフスクール、用品開発や販売、そしてメディア等、ゴルフ市場に身を置くものであれば皆が“自分事”として考えるべき問題。自分の領域だけのことを考えるのではなく、業界全体が一つになって取り組まなければならない問題だと感じました。
講演の中で松尾氏は「ゴルフ場が抱える課題」について言及されました。これはゴルフ場の問題を“自分事”として捉えるトリガーになったのではと思います。
その上で松尾氏は、ゴルフ場は現在のやり方をやめ、新たなやり方で成長する「改革」が必要だと述べ、必要な改革案を6つ提案。そして「新しいゴルファーを増やす」と「ゴルフ場を利用する人を増やす」の2つの側面から具体的に行動すべきだと訴えました。
そして後者の施策として、松尾氏自身が取り組む「ゴルフトライアスロン」と「ゴルファスロン」を紹介されました。「ゴルフトライアスロン」は、ゴルフと自転車、ランニングをミックスさせた競技。「ゴルファスロン」はゴルフとランニングのミックス競技です。

ランニング(ジョギング含む)人口やサイクリング人口はゴルフ人口よりも多い。このような人達にゴルフ場を訪れてもらい、ゴルフ場の魅力や素晴らしさを体感していただくことがこの取り組みの目的だと語られました。
そして最後に、「ゴルフ関係者は現実を見つめ直し、改革のための議論をはじめるべき」と締めくくりました。
松尾氏の講演を終えて出された意見はこちらです。(カッコ内は発言者、敬称略)
・「我々はもっと情報発信して危機意識を高めるべき」という指摘が心に刺さった。それに加え、情報発信するだけでなく、具体的な提案と行動が必要だと思う。(小森)
・小金井CCでは数年前から高卒の若い人材をキャディとして採用しているが、ゴルフに興味がない子供が非常に多い。採用しても自らゴルフを学ぼうとする意識が低い。どうしたらよいか策にあえいでいる。(井手口)
■松尾氏の講演資料は ▷こちら
■松尾氏の講演動画は ▷こちら ※本ミーティングの前段部分を含みます
今までのゴルフの概念をぶち破る発想を
後半の意見交換会は当初、ZOOMのブレイクアウトルーム機能を使い、2グループに分かれて実施する予定でしたが、当日キャンセルで参加者が少なくなったため、急遽グループ分けは行わず、全員参加によるフリーディスカッション形式で行いました。
出された主な意見は次の通りです。(カッコ内は発言者、敬称略)
・千葉セントラルGCは千葉県市原市にあり、同市は「ゴルフの街」として子供のゴルフ体験などにも力を入れている。このように行政を巻き込んで行うとよいと思う。そしてそのような事例を情報発信し、ゴルフ場を多く有する自治体に広めていきたい。(島崎)
・千葉セントラルGCでは地元の同好会に協力し、ウォーキングイベント会場として無料で貸し出している。このようにゴルフ場による地域密着の積極的な姿勢が大事。(島崎)
・高齢者のためのスローゴルフを提案。スローゴルフは9H、18Hを回るのが体力的にきつくなった高齢者を対象に、数ホールで良いので時間を気にせずゆっくり回ってもらおうというプレイスタイル。このことでゴルフリタイヤ年齢を延伸できると思う。(小森)
・ジュニアスクールで開催しているファミリーゴルフ大会のようなイベントは、家族でゴルフをはじめるきっかけづくりに良い。(小原)
・アート作品をゴルフ場に展示すると良いのでは。ゴルフ場も華やぎ、それを目当てに非ゴルファーも足を運ぶと思う。(小森)
・ゴルフの障壁の一つが拘束時間の長さと遠さ、そしてドレスコード。これら障壁を取り除き、今までのゴルフの概念をぶち破る発想が必要。(小川)
・小淵沢CCは隣にキースヘリング美術館があり提携している。また乗馬コースを新設したり、ワーケーション施設を整備したりと様々な事に取り組んでいる。更に腰痛の人を対象に中周波治療器をつけながらラウンドする等も実施。9月16日には「IKIGAI CUP」という試合も開催される。(小川)
・時短ゴルフはプロが時短トーナメント等で率先垂範することが大事。プレストウィックGCでの全英OPは元々6ホールからスタートしている。ゴルフの歴史上、6Hラウンドは原点回帰の意味もある。(浦東)
・ジュニア育成では、上手い子ばかりが注目される傾向は問題。戦績やプロ育成に偏り過ぎると普及啓蒙から離れていく。とはいえジュニア育成には競い合いも大事な要素。(浦東)
・2~3歳の年齢からフィールドをオープン化すると共に高齢者にも対象を広げる「ゆりかごから墓場まで」発想が必要。(浦東)
・高齢になると疾患や持病を持つ人も増える。そのような人達が安心してゴルフができる環境として「ゴルフと医療との連携」は不可欠。(小森)
また、メンバーシップ制からパブリック制に移行したゴルフ場の事例はあるかとの質問が出ましたが、参加者の中に分かる人が不在で、次回への宿題となりました。
次回は、11月25日(火)18時より開催を予定しています。
テーマは今回と同じ「日本のゴルフ場を魅力あるものにする」の続編です。
次回はゴルフ場事業者を招き、討論を深掘りしたいと思っています。
詳細は追ってお知らせいたします。
(文:小森)

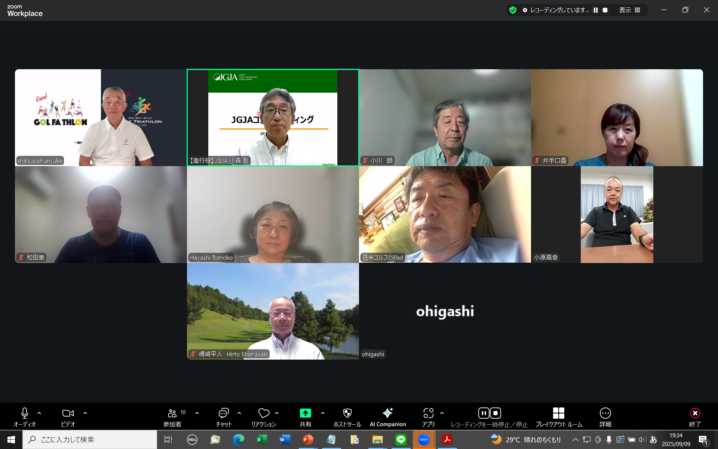

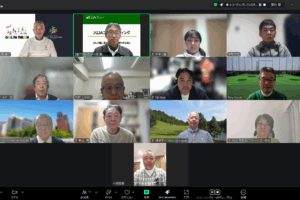
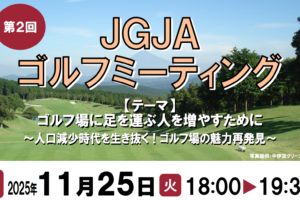
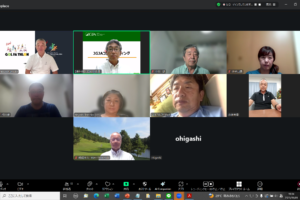
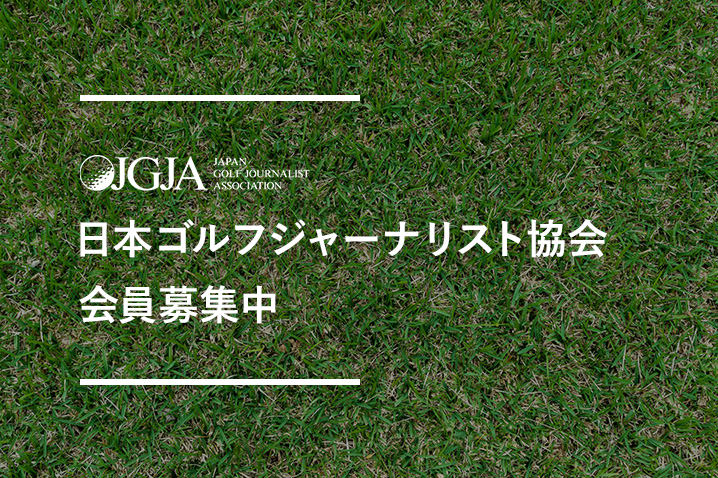

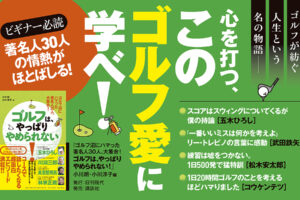


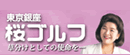




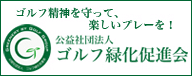


コメントを残す